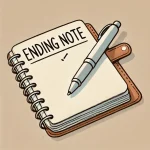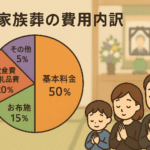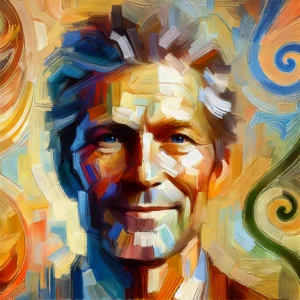【遺言・エンディングノート】遺言書がないとどうなる?終活で失敗しないための対策集
近年「終活」という言葉が広まりつつありますが、その中でも特に重要なのが「遺言書の作成」です。
遺言書は、自分が亡くなったあとに財産を誰にどう分けるかを指定できる法的な文書です。
しかし、実際には多くの人が遺言書を残さずに亡くなっており、その結果、家族間で深刻なトラブルに発展するケースも増えています。
「まだ元気だから大丈夫」「うちは家族仲が良いから揉めない」という思い込みが、相続問題を大きくする原因になることも。
この記事では、遺言書がないことによる5つのリスクと、それぞれに対する対策を詳しく解説します。終活を考えるすべての方に、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
相続トラブルで家族が争う

遺言書がない場合、財産は民法に基づいて「法定相続分」で分けられます。しかし、それが必ずしも家族全員にとって納得できる結果とは限りません。
特に多いトラブルの例は以下のとおりです。
- 不動産をどう分けるかで揉める(売却 or 相続)
- 長男・長女などに偏った分配を巡って兄弟姉妹が対立
- 面倒を見ていた家族に何も残らないことへの不満
こうした争いは、家族の絆を壊すだけでなく、裁判に発展して精神的・金銭的な負担が増すこともあります。
【対策】
遺言書により、財産の分配方法を具体的に明記しておくことで、家族間の争いを未然に防げます。
面倒を見た人が何ももらえない
生前、親の介護や日常の世話をしてくれた家族が、遺言書がないばかりに相続で不利になるケースもあります。
例として以下のような状況が挙げられます。
- 同居して介護を担っていたのに、財産は兄弟全員で均等に
- 法的には評価されない「感謝の気持ち」を形にできない
【対策】
遺言書で「○○には介護の感謝として多めに相続させたい」と明記することで、介護者の努力が報われる形になります。
相続人以外には財産を渡せない
遺言書がないと、配偶者や子、兄弟姉妹など法定相続人以外には、基本的に財産を残すことができません。
以下のような希望は遺言がなければ叶いません。
- 内縁のパートナーに遺産を残したい
- 孫や甥・姪に特別にお金を渡したい
- 長年お世話になった知人にお礼をしたい
- 慈善団体などに寄付したい
【対策】
遺言書で「誰に」「何を」「どのくらい」残すかを指定することで、自分の意志を尊重した相続が可能になります。
相続手続きが煩雑になる
遺言書がない場合、すべての相続人が集まって「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。これには以下のような手間がかかります:
- 全相続人の戸籍を調査・収集
- 相続財産の把握と整理
- 全員の署名と印鑑証明書が必要
相続人が全国に散らばっていたり、連絡が取れない相手がいると、手続きが滞ることも。
【対策】
公正証書遺言を作成しておくと、家庭裁判所の検認手続きが不要になり、手続きがスムーズに進みます。
財産が国のものになる可能性も
相続人がいなかった場合、残された財産は最終的に「国のもの」になります。
また、意図しない人(長年連絡のない親戚など)に財産が渡る可能性もあり、望まぬ結果になることも。
【対策】
遺言書を作成することで、財産の行方を自分の意志で決めることが可能です。
まとめ:遺言書は終活の要です
遺言書がないことで起きるトラブルは、誰にでも起こり得る現実です。
「相続争い」「家族の不満」「財産の迷子化」など、遺言書一つで防げる問題は数多くあります。
元気なうちにこそ、遺言書をしっかりと作成しておくことが、家族と自分を守る終活の第一歩です。
法的に有効な形式で残すためにも、公正証書遺言などの手続きについて、専門家に相談することをおすすめします。