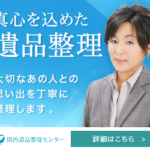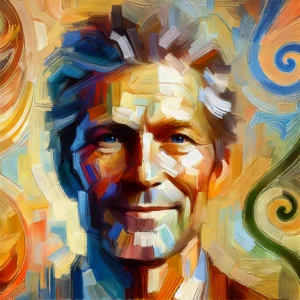【デジタル終活】終活でやるべきSNSアカウント削除
亡くなった後のSNS…放置していませんか?
スマートフォンの中にあるSNSアプリ。
Facebook、X(旧Twitter)、Instagramなどは、日常的に使う方も多いでしょう。けれど、自分が亡くなった後、それらのアカウントがどうなるか考えたことはありますか?
誰にも知られず、使われないまま放置されたSNSは、個人情報の流出や不正利用の原因にもなります。
この記事では、終活の一環としてSNSアカウントの削除方法を詳しく解説し、今できる「デジタル終活」の手順をわかりやすく紹介します。

終活 SNS アカウント削除の必要性とは?
SNSのアカウントは、亡くなった後もネット上に残り続けます。
そのままにしておくと、次のような問題が発生する可能性があります。
-
乗っ取りによる悪用
-
なりすまし投稿
-
知人からの連絡や誤認情報の拡散
-
家族が削除方法に困る
SNSは「思い出の記録」であると同時に、管理すべき個人資産でもあります。
終活の一部として、SNSの扱いを決めておくことは、自分のためにも、残された家族のためにも重要な準備です。
終活 SNS アカウント削除の基本ルール
SNSにはそれぞれ異なるポリシーがあり、「削除」だけでなく「追悼アカウント」という選択肢もあります。大きく3つの方法があります。
-
【1】生前に自分で削除または設定をする
-
【2】遺族が申請して削除・追悼に切り替える
-
【3】削除せずそのまま残すことを選ぶ
削除申請には、本人確認書類や死亡証明書などが必要になることがほとんどです。
また、削除処理には日数がかかることもあるため、事前の準備と共有がとても大切です。
終活 SNS アカウント削除 各社の方法【比較】
Facebook(フェイスブック)
-
【追悼アカウント】
故人のプロフィールに「追悼」の表示が出て、ログイン不可となります。
生前に「追悼アカウント管理者」を指定しておくと、故人の投稿へのコメント管理や、プロフィール写真の変更などが可能になります。 -
【削除】
死亡証明書や申請者の身分証を提出すれば、家族が削除申請を行えます。
削除するとすべての投稿や写真が消去され、復元できません。
X(旧Twitter)
-
【削除のみ】
追悼アカウントの機能はなく、削除のみの対応です。
家族がTwitter社のサポートフォームから申請し、必要書類(死亡証明書・本人確認書類など)を提出することで対応してもらえます。 -
【注意点】
削除処理には数週間かかることもあるため、早めの行動が推奨されます。
Instagram(インスタグラム)
-
【追悼アカウント】
申請すれば「追悼アカウント」に切り替えられます。名前の横に「追悼」の文字がつき、本人の投稿は残るものの編集・投稿不可となります。 -
【削除】
Facebook同様に、申請フォームと必要書類を送れば、削除手続きが可能です。 -
【連携注意】
InstagramとFacebookを同じアカウントで管理している場合でも、削除は別々に申請が必要です。
終活 SNS アカウント削除の注意点3つ
削除や追悼設定を行う前に、次の3点は必ず確認しておきましょう。
【1】写真・投稿のバックアップを取る
思い出の詰まった写真や動画、メッセージなどは、削除する前に必ず保存しておきましょう。SNSには「データをダウンロードする」機能が用意されている場合が多いです。
【2】削除後は復元できない
一度削除すると、アカウントの情報は完全に失われます。万が一のために、家族とも相談して慎重に判断することが大切です。
【3】なりすましや誤削除に注意
他人になりすまして削除申請を行うなどの悪用もあるため、申請時には正確な書類の提出が求められます。安全のためにも、公式フォームから行いましょう。
終活 SNS アカウント削除を家族に伝える方法
「自分が亡くなったらSNSをどうしてほしいか」は、しっかりと家族に伝えておきましょう。おすすめの方法は以下の通りです。
-
終活ノートに書く(SNS名と希望の処理を明記)
-
パスワード管理アプリに登録しておく
-
遺言書に記載する(法的効力が必要なら公正証書で)
例えばこう記載しておくと良いでしょう。
Instagramは追悼アカウント化、Xは削除してほしい
パスワードは〇〇というアプリに登録済み
記録を残すことで、家族が迷うことなく対応できます。
まとめ:今日から始めるデジタル終活
SNSアカウントは、今や自分の「デジタルな顔」のような存在です。
そのまま放置してしまうと、後で困るのは家族や友人かもしれません。
今からできること
-
よく使っているSNSを一覧にする
-
削除・追悼の希望をまとめておく
-
パスワードの保管先を家族に伝える
-
SNSごとの設定や申請方法を確認しておく
終活は「まだ早い」と思う人ほど、少しずつ始めることが大切です。
思い出とつながりを大切にしつつ、安心できる準備を進めていきましょう。