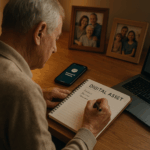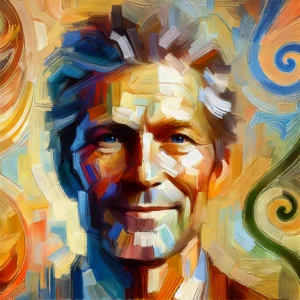【デジタル終活】終活 SNS アカウント削除 5つの手順|安心整理ガイド
終活にも“デジタル整理”が必要な時代へ
私たちの生活は、スマートフォンやSNSとともに歩んでいます。
写真の共有、友人との会話、思い出の記録――その多くはネット上にあります。
しかし、自分が亡くなった後、それらのデータはどうなるのでしょうか?
放置されたSNSアカウントは、知らない人に悪用されたり、家族にとって心の負担になったりすることがあります。
だからこそ「終活の一環としてSNSアカウントを整理・削除しておくこと」が大切です。
この記事では、誰にでもできる「終活SNSアカウント削除の5つの手順」を、わかりやすくご紹介していきます。
終活でSNSアカウント削除が必要な理由
デジタル遺品が家族に与える負担とは?
終活の目的は「残された人に迷惑をかけないこと」です。
SNSも例外ではなく、アカウントが残ったままだと、次のようなトラブルにつながることがあります。
✅ 家族が困るケース
-
ログイン情報が分からず削除できない
-
投稿内容をどう扱えばよいか判断に迷う
-
故人になりすましたアカウント乗っ取りリスク
たとえば、あなたがSNSに記録した日記や写真。
それを家族が見て「知らなかった一面」を知り、傷つく可能性もあります。
また、親しい人があなたの名前でDM(メッセージ)を受け取った場合、それが詐欺だったらどうでしょう。
こうしたトラブルを避けるために、「生きているうちにSNSを整理しておく」ことが重要なのです。
アカウントの悪用リスクを防ぐために
SNSアカウントが乗っ取られるリスクは、亡くなった後も続きます。
特に、パスワードが簡単だったり、長期間放置されたアカウントは狙われやすいのです。
乗っ取りによる悪用例
-
なりすましで詐欺メッセージを送る
-
アカウントに広告や違法商品を投稿
-
個人情報の抜き取りや拡散
こうした被害が起きると、残された家族が警察に相談したり、SNS運営会社に連絡したりしなければなりません。
これでは、本来静かに送るべき「故人とのお別れの時間」が、苦しい手続きに変わってしまいます。
だからこそ、悪用のリスクを減らすためにも、終活の段階での「アカウント削除」が大切になります。
終活 SNS アカウント削除 5つの手順とは?
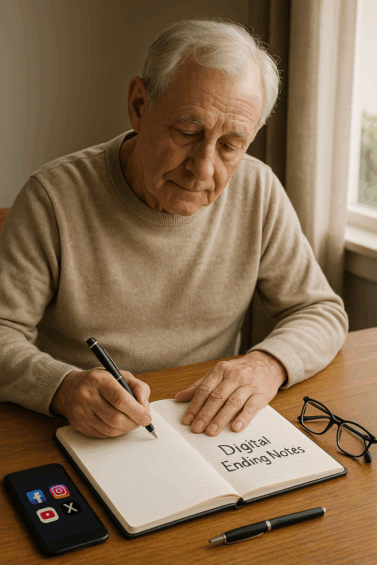
① 利用SNSをリストアップする
まず最初にやるべきことは、「自分が使っているSNSをすべて書き出すこと」です。
例:利用中のSNSリスト(例として記入)
-
Facebook(家族との交流)
-
Instagram(写真の記録)
-
X(旧Twitter)(趣味の発信)
-
LINE(連絡用)
-
TikTok(動画視聴)
-
YouTube(アカウントコメント)
-
Googleアカウント(Gmail・YouTube)
ここで大切なのは、「今使っていないけど昔登録したアカウント」も思い出して記入することです。
可能であれば、アカウントのIDや登録メールアドレスもメモしておくと、後の削除手続きがスムーズになります。
② 各SNSの削除・停止方法を確認
SNSごとに、アカウントを削除する手順や、遺族が申請できる仕組みは異なります。
そのため、あらかじめ公式サイトで確認しておくことが重要です。
SNS別:対応の例
-
Facebook:追悼アカウント設定または削除申請
-
Instagram:死亡証明書を出して遺族が申請
-
X(旧Twitter):死亡確認書類を提出し削除依頼
-
LINE:端末の初期化、またはアカウント削除
操作方法や手続きに必要な書類は、SNSの公式「ヘルプセンター」に詳しく記載されています。
ブックマークしておくか、エンディングノートにURLを書いておくと安心です。
③ 遺族が削除申請できる設定を行う
Facebookなど一部のSNSでは、あらかじめ「追悼アカウント管理者」や「代行者」を設定できるようになっています。
これは、あなたが亡くなった後、信頼できる人がアカウントを操作できるようにする機能です。
具体的な設定例(Facebookの場合)
-
設定 → 記念アカウント → 管理者を選ぶ
-
追悼アカウントとするか、完全削除にするかの希望を記録
また、スマートフォンやパソコンのロック解除方法を信頼できる家族に伝えておくと、他のSNSへのアクセスも可能になります。
④ パスワード管理を見直す
アカウント削除において、最も重要かつ忘れがちなのが「パスワード管理」です。
整理のポイント
-
すべてのSNSのログインIDとパスワードをリスト化
-
紙のノートに手書きし、安全な場所に保管
-
パスワードを家族に伝える手段を用意
-
デジタル管理アプリを使用する場合は、アプリ自体のパスワードも共有
終活の観点から言えば、「デジタルではなく紙で残す」ことが推奨されます。
もし電子管理を選ぶ場合は、バックアップや復旧手順も記録しておきましょう。
⑤ メモやエンディングノートに記録する
最後に、すべての情報を「エンディングノート」や「終活メモ」としてまとめましょう。
記録するべき内容
-
利用中のSNSの一覧
-
削除または保存の希望(例:Facebookは残したい)
-
削除手続きに必要なログイン情報
-
管理を任せたい家族の名前
ノートは紙に書く方法が一番安心ですが、最近は「終活アプリ」や「デジタルノート」も選択肢として増えています。
大切なのは「見つけてもらえるように保管すること」です。
代表的なSNSごとの削除・追悼手続き
Facebook:追悼アカウントと削除の違い
Facebookには、以下の2つの方法があります。
-
追悼アカウント
故人の投稿を残し、プロフィールに「追悼」と表示されます。生前に設定が必要です。 -
完全削除
遺族が死亡証明書を提出し、アカウントそのものを削除します。
選択は本人の希望に沿って行われます。設定は、Facebookヘルプセンターを参考にしてください。
Instagram:遺族による削除申請方法
Instagramでは、本人が亡くなった後に遺族が削除申請を行います。
削除に必要なのは、以下のような書類です。
-
死亡証明書(戸籍抄本など)
-
故人との関係を証明する書類(家族関係証明)
申請フォームから手続きができます。Instagram公式ヘルプで確認できます。
X(旧Twitter):本人・遺族の対応手順
Xでは、次の2つの方法があります。
-
本人が生前に削除する
-
死亡後、遺族がフォームから申請(身元確認が必要)
申請には、故人の情報とあなた(申請者)の身分証明書が必要です。
手続きはTwitterヘルプセンターで詳細確認できます。
SNS削除以外にできるデジタル終活
スマホ・クラウドのデータ整理
SNSのほかにも、以下のようなデジタルデータも整理しておくと安心です。
-
写真・動画の保存
-
クラウドサービス(Google Driveなど)の中身確認
-
不要なアプリ・契約の解約
特にGoogleアカウントはGmailやYouTubeにも関係するため、慎重な整理が必要です。
写真・動画のバックアップと共有
スマホの中には、家族との大切な思い出が詰まっています。
それらをきちんとバックアップし、家族と共有する準備をしておきましょう。
共有の方法例
-
Googleフォトに家族共有アルバムを作る
-
USBや外付けHDDに保存しておく
-
写真を印刷してアルバムにまとめる
「見える形で残す」ことで、思い出は家族の宝物になります。
SNSアカウント削除の注意点とまとめ
削除前に必ず確認したい3つのこと
削除すると元に戻せないため、以下は必ず確認してください。
-
大切な写真・投稿が残っていないか
-
他サービスと連携していないか(LINE Pay、Googleログインなど)
-
重要な連絡先や履歴が残っていないか
後悔しない終活のコツとは?
終活は「やらなきゃ」と思っていても、なかなか進まないものです。
しかし、一歩ずつ小さな作業から始めれば、必ず終わりが見えてきます。
おすすめの進め方
-
SNSを1つずつ整理していく
-
エンディングノートに書き足していく
-
家族と話し合いながら進める
今やることで、家族もあなた自身も安心して未来を迎えられます。