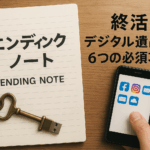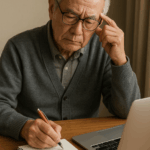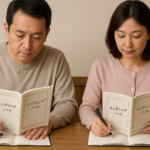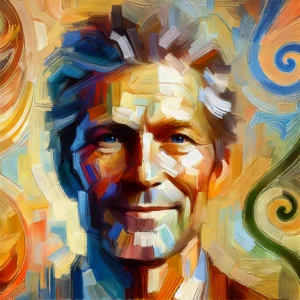【デジタル終活】終活で見落としがちなデジタル遺品5選!今からできる準備とは?
インターネットやスマートフォンが生活の一部となった今、「デジタル遺品」は避けては通れない終活の課題となっています。
スマホやPCに眠る写真、SNSアカウント、ネット銀行の情報など、見えないデジタルの遺品をどう整理するかは、残された家族にとっても重要です。
この記事では、終活の一環として「デジタル遺品」をどう準備すればいいか、今から実践できる5つの方法を具体的に紹介します。
終活で整理すべき「デジタル遺品」とは?
デジタル遺品とは、故人が生前に使っていたスマートフォン、パソコン、インターネット上のデータや契約情報のことを指します。以下のようなものが含まれます。
-
写真や動画などのデータ
-
GmailやLINEなどの通信履歴
-
SNSアカウント(X、Instagram、Facebookなど)
-
ネット銀行・証券口座・仮想通貨の情報
-
月額サブスクの契約(Netflix、Amazonなど)
-
オンラインストレージのデータ(Googleドライブ、Dropboxなど)
これらは目に見えない資産であり、放置すると家族がアクセスできず、相続トラブルや情報流出のリスクを招くことがあります。
デジタル遺品を放置すると起こるリスクとは?
デジタル遺品を整理せずに亡くなると、家族が苦労する原因になります。以下のようなトラブルが実際に報告されています。
-
ネット銀行や仮想通貨の資産に家族がアクセスできない
-
SNSアカウントが残ったままになり、誤解やトラブルの元になる
-
有料サービスの支払いが継続し、解約できずに無駄な出費が続く
-
思い出の写真や動画が失われる可能性がある
-
不正利用や個人情報の流出に繋がるおそれがある
デジタル遺品は放置しても自然には整理されません。自分が元気なうちに準備しておくことが大切です。
デジタル遺品を整理する5つの準備方法

今すぐ始められるデジタル遺品の整理法を5つご紹介します。
1. 紙に情報をまとめて一覧化する
まずは、パスワードやログイン情報などを「紙」に書いて残しておきましょう。
-
メールアドレスとその使用先
-
SNSやネットバンクのIDとパスワード
-
契約中のサブスクやポイントサービス
-
写真や動画が保管されているサービス名
エンディングノートや専用のメモ帳などに記録し、金庫や机の引き出しに保管しておくとよいでしょう。
2. 家族に情報をきちんと伝える
情報を残しても、誰にも伝えていなければ意味がありません。
-
メモの保管場所を伝えておく
-
信頼できる人に「デジタル担当者」をお願いする
-
口頭だけでなく、メモや手紙でも意思を残す
家族に情報が確実に伝わるよう、何らかの「伝達方法」を決めておきましょう。
3. 終活アプリやノートを活用する
最近は、スマホで手軽に使える終活アプリやクラウド型ノートも登場しています。
-
らくらくエンディングノート(アプリ)
-
マイノートCloud(オンライン型)
-
市販のエンディングノート(手書き用)
紙とアプリを併用することで、情報管理がしやすくなります。
4. 不要なアカウントを削除する
使っていないSNSやサービスのアカウントは今のうちに削除しておきましょう。
-
使っていないメールアカウント
-
昔登録した会員サイト
-
解約忘れの有料サービス
余分なデジタル資産を減らすことで、家族の負担も軽くなります。
5. 死後の希望を明文化しておく
デジタル情報の扱いについて「どうしてほしいか」をはっきりさせておくと安心です。
-
SNSは削除してほしいのか、残してほしいのか
-
写真や動画の扱いについての希望
-
仮想通貨やポイントの相続先
終活ノートにメモしておくだけでも、遺族にとっては大きな助けになります。
デジタル遺品の専門相談も活用しよう
個人で整理するのが難しい場合は、専門家の力を借りるのもひとつの手です。
-
行政書士・司法書士の終活相談
-
パソコンやスマホのデータ整理専門業者
-
地域の終活セミナーや無料相談会
高齢の方は特に、家族と一緒に相談することで、スムーズに情報整理が進みます。
まとめ|デジタル遺品の整理は今から始めよう
デジタル遺品は、目に見えないからこそ整理を後回しにされがちです。しかし、残された家族の負担を減らすためには、生前からの準備が欠かせません。
今日からできるポイント
-
紙でもアプリでもよいので、情報をまとめる
-
家族にその存在を伝える
-
不要な情報は早めに削除しておく
あなたの想いや大切な情報を、確実に届けるために。今日から、無理のないペースで「デジタル終活」を始めてみましょう。