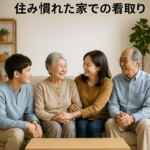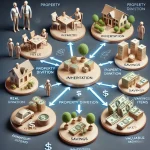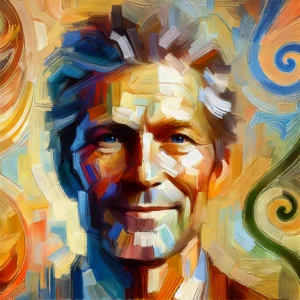【遺言・エンディングノート】終活におけるエンディングノートと遺言書の違いとは?法的効力を持たせるためのポイント
終活を進める中で、自分の最期について考えたときに「エンディングノート」と「遺言書」の違いに戸惑う方は多いのではないでしょうか?
どちらも大切な記録ですが、実は法的な効力には大きな違いがあります。
本記事では、エンディングノートの役割や限界、遺言書との違い、そして確実に意思を残すための方法をわかりやすく解説します。
エンディングノートとは?終活における役割
エンディングノートとは、自分の希望や思いを家族や大切な人に伝えるためのノートで終活の一環として多くの方が活用しています。
以下のような内容を自由に記録できます。
-
氏名、生年月日、家族構成などの基本情報
-
医療・介護の希望(延命治療の有無など)
-
葬儀やお墓の希望(形式、場所、宗教など)
-
財産の所在や保険の情報
-
デジタル遺産の管理(SNSや口座情報)
-
家族や友人へのメッセージ
エンディングノートに決まった形式はなく、書きたい内容を自由に記入できます。
そのため、自分の想いを整理し、家族の負担を減らすためにも非常に有用です。
エンディングノートに法的効力はあるのか?
結論から申し上げますと、エンディングノートには法的効力はありません。
どれだけ丁寧に記載されていても、法的な拘束力はなく、相続や財産分配においては無効とされる可能性があります。
たとえば、「この家は長男に譲りたい」と書いても、正式な遺言書でなければ、その意志が法的に守られることはありません。
東京弁護士会なども、エンディングノートはあくまで「意思を伝えるツール」であり、法的文書ではないことを明記しています。
遺言書との違いとは?表で比較してみよう
エンディングノートと遺言書は、どちらも人生の終盤を整理するツールですが、目的や効力が異なります。以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 記載形式 | 自由 | 法律で定められた形式が必要 |
| 主な目的 | 気持ちや希望の共有 | 財産分配や法的手続き |
| 作成の自由度 | 誰でも自由に記入できる | 条件を満たさないと無効 |
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの形式があり、条件を守って初めて有効となります。一方で、エンディングノートは気軽に記録できる反面、法的な裏付けはありません。
法的効力を持たせたいなら遺言書を準備しよう

「財産を誰に渡したいか」「相続で揉めてほしくない」とお考えであれば、法的効力のある遺言書を用意しましょう。遺言書には次のような形式と注意点があります。
自筆証書遺言の場合
-
全文を自分で手書きすること
-
日付、署名、押印が必要
-
2020年からは法務局での保管制度もスタート
公正証書遺言の場合
-
公証人の立会いのもと作成
-
手続きが厳密で信頼性が高い
-
費用はかかるがトラブル回避には有効
特に法務局による自筆証書遺言保管制度は、安心して保管できる新しい選択肢です。
エンディングノートと遺言書を併用するのがおすすめ
エンディングノートと遺言書は、役割が異なるため、両方を使うことでよりスムーズな終活が可能になります。
併用のメリット
-
想いと法的手続きをしっかり分けて記録できる
-
家族が迷わず対応できるため精神的負担が減る
-
書いていないことへの補足説明ができる
-
気持ちを文字で残せることで、遺族の心の支えにもなる
たとえば、遺言書で「家は長女へ相続」と記し、エンディングノートでは「家を大切に守ってくれてありがとう」と気持ちを伝えることで、形式と心情の両面から円満な相続を促せます。
意思を「伝える」だけでなく「遺す」準備を
終活において、エンディングノートと遺言書の違いを理解し、適切に使い分けることが大切です。
エンディングノートには思いを伝える力がありますが、法的に家族を守るためには遺言書が必要不可欠です。
要点まとめ
-
エンディングノートは法的効力がない
-
遺言書は条件を満たせば法的に有効
-
両者を併用することで、心と法律の両面から安心を得られる
これから終活を始める方は、まずはエンディングノートで思いを整理し、その後遺言書の作成を検討することをおすすめします。大切な家族に、自分の意思をしっかりと遺してあげましょう。